「新築住宅を建てたいけど、完成後に不備があったらどうしよう」
「新築住宅ではどんなことが保証されているの?」
新築住宅を建てる上で、上記のような悩みに直面する方は多いでしょう。施工会社の悪い口コミや評判を見聞きしてしまうと、施工を依頼していいのか不安になってしまいます。そのため、新築住宅における保証を知ることが大切です。
住宅完成後のトラブルはないことに越したことはないですが、万が一に備えておく必要があります。新築住宅における保証内容が理解できていれば、瑕疵が発覚したときでもスムーズに対応できるでしょう。
この記事では、新築住宅における保証の種類や期間、内容について解説します。各施工会社の保証内容が充実しているかを見極めるコツについても触れているため、ぜひ参考にしてみてください。
また、以下の記事では岡山でおすすめの住宅メーカー3選を紹介していますので、会社選びでお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
そもそも新築住宅の保証とは?

新築住宅を購入したり建てたりする際に、「保証」は欠かせない安心要素のひとつです。建物は長期的に住み続けるものだからこそ、万が一の不具合や欠陥に備える制度が整えられています。
特に、構造上の安全性や防水性能は法律で保証が義務づけられており、購入者を守るための仕組みとして設けられています。
ここでは、新築住宅の保証制度の基本を3つの観点からわかりやすく解説します。
これらを理解しておくことで、契約時に保証内容を正しく把握し、建てた後も安心できるマイホームを実現できるでしょう。以下で詳しく解説します。
新築住宅には保証が義務づけられている理由
新築住宅には、構造や防水に関する欠陥を補修する「保証」が法律で義務づけられています。これは、住宅購入者を保護するために制定された「住宅品質確保促進法(品確法)」によるもので、施工会社や売主には引き渡しから10年間、欠陥を補修する義務があります。
この保証制度は、施工不良や業者の倒産などのリスクから購入者を守る目的で設けられました。住宅の品質と安全性を確保し、安心して暮らせる住まいを提供するために欠かせない制度です。
保証の対象となる範囲は?
保証の対象となるのは、住宅の中でも特に安全性や耐久性に関わる重要な部分です。
主な対象は「構造耐力上主要な部分(基礎・柱・梁など)」と「雨水の侵入を防止する部分(屋根・外壁など)」です。これらの部分に欠陥が発生した場合、施工会社は無償で補修する義務があります。
また、キッチンや浴室などの住宅設備に関しては、メーカーによる短期保証(1〜2年)が適用されるのが一般的です。どの範囲が保証対象となるかを契約前に確認しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
住宅品質確保促進法による基準
「住宅品質確保促進法(品確法)」は、住宅の品質を一定水準で保つために制定された法律です。
この法律により、施工会社や売主は、構造・防水に関する欠陥が発生した際に10年間の補修責任を負います。さらに、施工会社が倒産した場合でも、住宅瑕疵担保責任保険制度を通じて購入者が補償を受けられる仕組みも整えられています。
つまり、品確法は「建てた後の安心」を守るための法律であり、購入者が安全で長く住める家を手に入れるための基盤となっています。
新築住宅で保証される主な種類は?

新築住宅の保証には、住宅購入者が安心して長く住めるようにするための仕組みが整えられています。保証の対象は建物の構造や防水部分、キッチンなどの設備など、部位によって内容や期間が異なります。
また、国が法律で定めている保証と、ハウスメーカーや工務店が独自に設けている保証の2種類が存在します。
ここでは、それぞれの保証の特徴をわかりやすく解説します。
これらを理解しておくことで、契約前に「どこまでが保証対象なのか」を把握し、後悔のない家づくりができるでしょう。以下で詳しく解説します。
家の構造や屋根など「建物の基本部分」を守る保証
新築住宅の中でも最も重要なのが、建物の安全性を守る「基本構造部分」に関する保証です。
柱や梁、基礎といった構造耐力上主要な部分や、屋根・外壁などの防水部分は、住宅品質確保促進法(品確法)によって10年間の保証が義務づけられています。
この保証は、地震や強風などで構造部分に不具合が生じた場合、施工会社が無償で補修・修繕を行うというものです。長期間にわたって建物の安全性を支えるため、家を建てる際には最も重要視すべき保証といえるでしょう。
キッチンやお風呂など「設備部分」を守る保証
住宅設備に関する保証は、主にメーカーや施工会社が独自に定めているもので、1〜2年程度の短期保証が一般的です。
キッチン・トイレ・給湯器・浴室など、生活に欠かせない設備が対象で、初期不良や設置ミスによるトラブルがあった場合に無償修理が受けられます。ただし、経年劣化や使用上の不注意による故障は対象外です。
メーカーによっては有償で保証期間を延長できるサービスもあるため、契約前に確認しておくことが大切です。設備は毎日使う部分なので、保証の有無が暮らしの快適さを左右します。
国の法律で決められた「義務保証」
新築住宅のうち、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防ぐ部分については、国の法律(品確法)により10年間の保証が義務づけられています。
これは、建築会社や売主が10年間、欠陥が発生した場合に修繕や補修を行う責任を負うという制度です。さらに、施工会社が倒産してしまった場合でも、「住宅瑕疵担保責任保険」によって購入者は補償を受けられる仕組みがあります。
この制度によって、家を購入したあとも安心して住み続けられる環境が整備されています。
ハウスメーカーや工務店が独自に設けている「延長・追加保証」
ハウスメーカーや工務店では、法律で定められた10年保証に加えて、独自の延長保証や追加保証を設けている場合があります。
たとえば、構造保証を20年〜30年に延長できるプランや、外壁・防蟻処理・設備機器などに対する独自の保証が用意されているケースもあります。これらの保証内容や期間、条件は会社によって異なるため、契約前にしっかり確認しておくことが重要です。
特に、定期点検を継続することで延長保証が適用される場合が多く、長く安心して暮らしたい人にとって心強いサポートとなるでしょう。
新築住宅の保証期間は?

新築住宅の保証期間は、保証の対象によって異なります。保証期間を理解しておくことで、将来的な修繕費やメンテナンス費を見越した計画が立てやすくなります。
ここでは、新築住宅の主な保証期間と、万が一のトラブル時の対応について解説します。
それぞれの保証内容と期間を把握しておくことで、安心して長く住み続けることができます。以下で詳しく解説します。
構造・防水は10年間の義務保証
新築住宅のうち、柱・梁・基礎などの「構造耐力上主要な部分」と、屋根・外壁などの「雨水の侵入を防止する部分」については、住宅品質確保促進法(品確法)により10年間の保証が義務づけられています。
この期間内に構造上の欠陥や雨漏りなどが発見された場合、施工会社や売主が無償で修繕を行う責任を負います。10年という期間は、住宅の耐久性を維持するために最低限必要とされる年数です。
引き渡し後は定期的に点検を受けることで、保証がしっかり適用される状態を保てます。
内装・設備などの短期保証期間(1〜2年)
構造部分とは異なり、キッチン・トイレ・お風呂などの住宅設備や、壁紙・床などの内装は「短期保証」の対象となります。一般的に1〜2年程度の保証が設けられており、施工不良や初期不具合が発見された場合に無償で修理を受けられます。
ただし、経年劣化や使用上の不注意による損傷は保証の対象外です。住宅会社によっては、設備保証を5〜10年に延長できるオプションを用意している場合もあります。
契約時には、保証期間の確認と延長制度の有無をチェックしておくことが重要です。
施工会社が倒産した場合の対応(保証保険制度)
新築住宅を建てた施工会社が倒産してしまった場合でも、購入者が保証を受けられるように整備されているのが「住宅瑕疵担保責任保険制度」です。
この制度により、万が一施工会社が修繕を行えない状態になったとしても、保険会社が修理費用を補償してくれます。保証対象は、構造上主要な部分や防水部分など、品確法で定められた範囲に限定されますが、住宅購入者の経済的なリスクを軽減する仕組みです。
家を建てる前に、施工会社がこの保険に加入しているか必ず確認しましょう。
新築住宅の保証で気をつけるべき3つの注意点

ここでは、保証制度をしっかり活用するために押さえておきたい3つの注意点を紹介します。
それぞれの注意点を理解しておくことで、保証を無駄にせず、住宅の資産価値を守ることができるでしょう。以下で詳しく解説します。
保証が切れる前に定期点検を受ける
保証期間を有効に保つためには、定期点検を必ず受けることが重要です。多くのハウスメーカーや工務店では、引き渡し後1年・5年・10年といった節目で無料点検を実施しています。
点検を怠ると保証が失効してしまう場合もあるため、スケジュールを把握しておきましょう。
また、点検時に軽微な不具合を早期発見することで、大規模な修繕を防ぐことにもつながります。点検は単なる形式ではなく、家を長持ちさせるための大切なメンテナンスの一環です。
リフォーム・DIYで保証が無効になる場合がある
住宅の保証は、建てた当時の状態を前提として適用されます。そのため、保証期間中にリフォームやDIYで構造や防水部分に手を加えると、保証が無効になるケースがあります。特に、屋根や外壁、配管などを自分で改修した場合は注意が必要です。
リフォームを行う際は、施工会社や住宅メーカーに必ず相談し、保証を維持できる工事方法を確認しておきましょう。勝手な改修は、保証だけでなく建物の安全性にも影響を及ぼす可能性があります。
自然災害や経年劣化は保証対象外になる
住宅保証は、施工不良や欠陥など「人為的な原因」による不具合を補修するためのものです。地震・台風・洪水などの自然災害や、時間の経過による経年劣化は保証の対象外となります。
ただし、火災保険や地震保険などの損害保険に加入していれば、こうした被害にも対応できます。住宅の長期的なリスクに備えるため、保証制度と保険の両方をバランスよく活用することが大切です。
保証と保険の違いを理解しておくことで、万が一の際にも安心して対処できます。
新築住宅の保証トラブルを防ぐためのチェックリスト

新築住宅の保証は、万が一の不具合や欠陥が発生した際に購入者を守る大切な仕組みです。しかし、契約内容を正しく理解していなかったり、必要な書類を受け取っていない場合、いざという時に「保証が使えない」というトラブルに発展することもあります。
そこで、契約前から引き渡し後までに確認しておきたいポイントを、わかりやすくチェックリスト形式で紹介します。
これらを事前に把握しておくことで、保証の使い忘れや対応漏れを防ぎ、安心して新生活をスタートできます。以下で詳しく解説します。
契約前に確認しておくべき保証項目
契約を結ぶ前に、保証の範囲や内容をしっかり確認しておくことが重要です。特に、構造・防水・設備など、どの部分が保証対象になるのか、保証期間がどのくらいあるのかを明確にしておきましょう。
ハウスメーカーや工務店によって保証内容が異なるため、下記のような項目を比較するのが効果的です。
| 確認項目 | 内容 | 保証期間の目安 |
|---|---|---|
| 構造部分 | 柱・梁・基礎など主要構造部 | 10年(法定保証) |
| 防水部分 | 屋根・外壁・バルコニー防水など | 10年(法定保証) |
| 設備機器 | 給湯器・トイレ・キッチンなど | 1〜2年(メーカー保証) |
| 内装仕上げ | 壁紙・床・建具など | 1〜2年(短期保証) |
これらの項目を確認しておけば、保証が必要な場面で慌てることなく対応できます。契約前に「保証範囲」と「保証期間」を書面で残しておくことがトラブル防止の第一歩です。
引き渡し時に受け取るべき書類一覧
住宅の引き渡し時には、保証を受けるために必要な書類が複数あります。これらの書類は、将来的に修理や点検を依頼する際に必ず必要となるため、紛失しないよう整理して保管しておきましょう。
| 書類名 | 内容 | 保管のポイント |
|---|---|---|
| 契約書・保証書 | 保証内容・期間・条件の記載 | 原本をファイルに保管 |
| 住宅瑕疵担保責任保険証 | 保険加入の証明書 | 保険会社の連絡先も一緒に記録 |
| 設備保証書 | 各メーカーの保証内容 | 機器ごとに分けて保管 |
| 図面・仕様書 | 建物の構造・使用材料の詳細 | メンテナンス時に参照可能 |
| 引き渡し確認書 | 受領内容・不具合の有無を記録 | サイン後のコピーを保管 |
引き渡し後に保証を利用する場合、これらの書類がないと対応が遅れるケースもあります。ファイルやクラウド上で整理して、いつでも確認できるようにしておくと安心です。
新築住宅の保証が手厚い注文住宅会社を選ぶコツ

新築住宅を購入する際、住宅の品質保証やアフターサービスが充実しているかどうかは非常に重要なポイントです。
家は長期間住む場所であり、もしもの場合に備えてしっかりとした保証がある会社を選ぶことが、後悔しない家づくりにつながります。
手厚い保証がある会社を選ぶことで、将来の不安を減らし、安心して長く住み続けることができます。
以下に、信頼できる注文住宅会社を選ぶためのコツをまとめました。
・独自の長期保証・アフターサービスを比較する
・定期点検やメンテナンスサポートの充実度を確認する
・口コミ・施工事例で対応力をチェックする
・信頼できる注文住宅会社に依頼する
これらのポイントを意識することが大切です。
信頼できる注文住宅会社の選び方

家を建てる際、信頼できる注文住宅会社を選ぶことは、成功する家づくりのための第一歩です。信頼できる会社を選ばないと、理想的な住まいが完成しないだけでなく、途中で予期しないトラブルや追加費用が発生することもあります。
自分の希望に沿った家を作るためには、どんな会社が適しているのか慎重に選ぶことが大切です。
以下では、信頼できる注文住宅会社を選ぶためのポイントをまとめました。
・実績が豊富で地域に根ざした会社を選ぶ
・担当者の対応力と提案力をチェックする
・複数社を比較して選ぶ
これらのポイントを理解し実践することで、より理想的な住まいを実現できる会社を見つけることができ、安心して家づくりを進められるでしょう。
岡山県でおすすめの注文住宅会社3選
最後に、岡山県でおすすめの注文住宅会社を3つ紹介します。
それぞれの注文住宅会社について解説します。
タカ建築
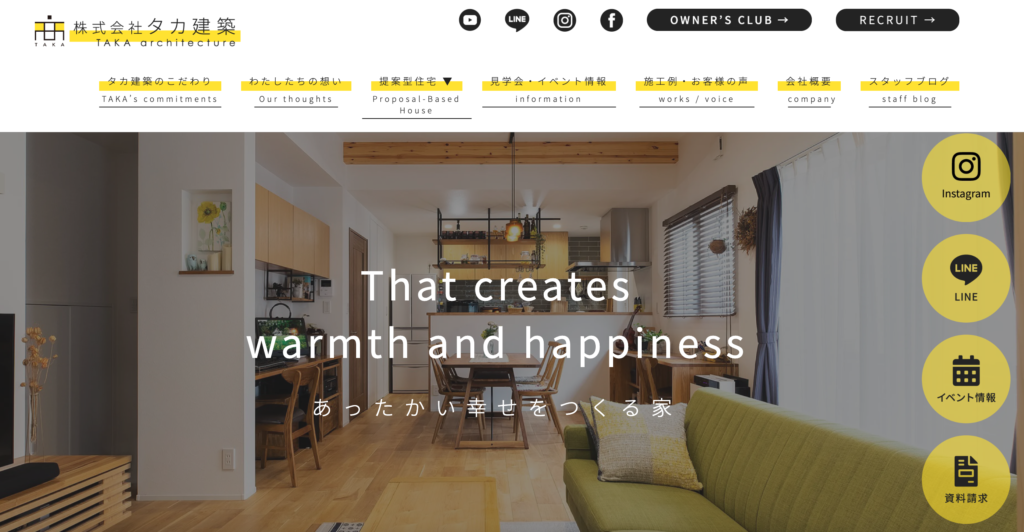
創業35年のタカ建築は、アフターフォローが充実した地域密着型の注文住宅会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社タカ建築 |
| 所在地 | 岡山市北区白石西新町7-123 |
| 設立年月日 | 1988年3月 |
| 対応地域 | 岡山市、倉敷市、早島町、総社市、玉野市、備前市、赤磐市、瀬戸内市 |
| 公式サイト | https://takaken-okayama.com/ |
建物初期保証20年に加え、シロアリ保証5年(最大500万円)、地盤保証20年(最大5,000万円)、住宅設備保証10年と、充実の保証が魅力です。
スーパーウォール工法にも対応し、高断熱の住宅設計を得意としています。引き渡し後のトラブル対応サービスもあるため、新築住宅の保証について不安を抱いている方におすすめです。
なお、タカ建築についてより詳しく知りたい方は、公式サイトを訪れてみてください。
また、以下の記事ではタカ建築の口コミや評判、会社の特徴や施工事例などを解説していますので、気になる方はぜひ一度チェックしてみるといいでしょう。
アイ工務店

アイ工務店は、デザインや設備を重視したい方におすすめの注文住宅会社です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社アイ工務店 |
| 会社住所 | 大阪市中央区心斎橋筋1-9-17エトワール心斎橋9F |
| 創業年数 | 2010年7月13日 |
| 対応エリア | 全国各地 |
| 公式サイト | https://www.ai-koumuten.co.jp/ |
お客様それぞれの理想を形にするプロデュースが特徴で、細部までこだわったデザインを提供してくれます。
他にもローコストでの建築や万全の保証・サポート体制など、初めて家を建てるという方にもおすすめです。実績のある施工会社に依頼したい方は、アイ工務店を検討してみてください。
また、以下の記事ではアイ工務店について詳しく解説しているので、是非参考にしてください。
一条工務店

ブランド力を重視し、高性能の住宅を建てられるのが一条工務店です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社一条工務店 |
| 会社住所 | 東京都江東区木場5-10-10 |
| 創業年数 | 1978年 9月 |
| 対応エリア | 全国 |
| 公式サイト | https://www.ichijo.co.jp/ |
耐震性だけでなく、断熱性、気密性などが高水準で設計され、実大実験を経て商品として売り出されます。
保証やアフターフォローも充実していて、トラブル時にも素早く対応してくれます。住宅展示場出展棟数業界No.1・年間1万件以上といった確かな実績もあるため、住宅の品質にこだわりたい方は一条工務店がおすすめです。
以下の記事では、一条工務店について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください
まとめ
新築住宅の保証は、法的義務のある保証に加え、施工会社ごとに保証を設定できます。保証については、契約不適合責任や瑕疵担保責任保険、住宅瑕疵担保履行法を理解しつつ、各施工会社の保証内容を十分に確認することが大切です。
契約内容に盛り込まれる保証の範囲や期間を確かめれば、契約締結後のトラブルを防げるでしょう。保証内容を把握できていれば、安心して暮らせます。新築住宅を建てようとしている方は、保証に関する法律や責任について理解しておきましょう。











